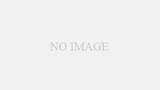小児の肝機能障害の看護計画
#1安静が守れないことに関連して肝血液量の低下する可能性がある
目標:肝機能が悪化しない
O-P
1 検査データ:肝機能
2 患児の行動、言動
3 バイタルサイン
T-P
1 患児が理解できるように説明する
2 規制された日常生活面への援助の程度を明確にする
3 患児の精神的慰安を図る
a 乳幼児期の場合は家族の付き添いを促し協力を得る
b 学童期の場合は家族の面会を促し協力を得る
4 頑張り表などを作成して、食後の安静が守れるように働きかける
5 学童期の患児には検査結果を知らせると同時に、安静の効果について理解できる方法を一緒に考える
6 患児の好きな遊び興味のあることに視点を当てて遊びを工夫する
EーP(教育)
1 患児家族に安静の必要性を説明し協力を得る
#2食欲不振に関連して、肝臓に必要な栄養が補給されない可能性がある
目標:患児の好きな食品がバランスよく摂取できる
O-P
1 食欲
2 食事摂取量、摂取カロリー
3 食事に対する不満
4 体重の増減
5 検査データ:肝機能、血性蛋白
T-P
1 食事をする環境に変化を持たせる:場所を変える。同年代の患児、母親と一緒に食べる
2 食べたいと思った時に、回数を分けて摂取できるようにする
3 食事の内容に変化を持たせる
4 状況によっては栄養指導を栄養士へ依頼する
#3黄染による皮膚の掻痒感に関連して精神的慰安が保てない可能性がある
目標:搔痒感が緩和される
O-P
1 皮膚の状態:黄染、かき傷
2 爪
3 搔痒感
4 機嫌
5 検査データ:血中ビリルビン
6 睡眠
T-P
1 清拭又は座浴を行い、身体の清潔を保つ
2 搔痒感がる場合
a 爪を切り皮膚を傷つけないよう必要に応じて手袋を使用する
b 叩くさするの方法を用いかきむしらない
c 冷罨法をする
d 患児の遊びを工夫し気を紛らわせる
EーP(教育)
1 掻痒時の対応方法について説明する